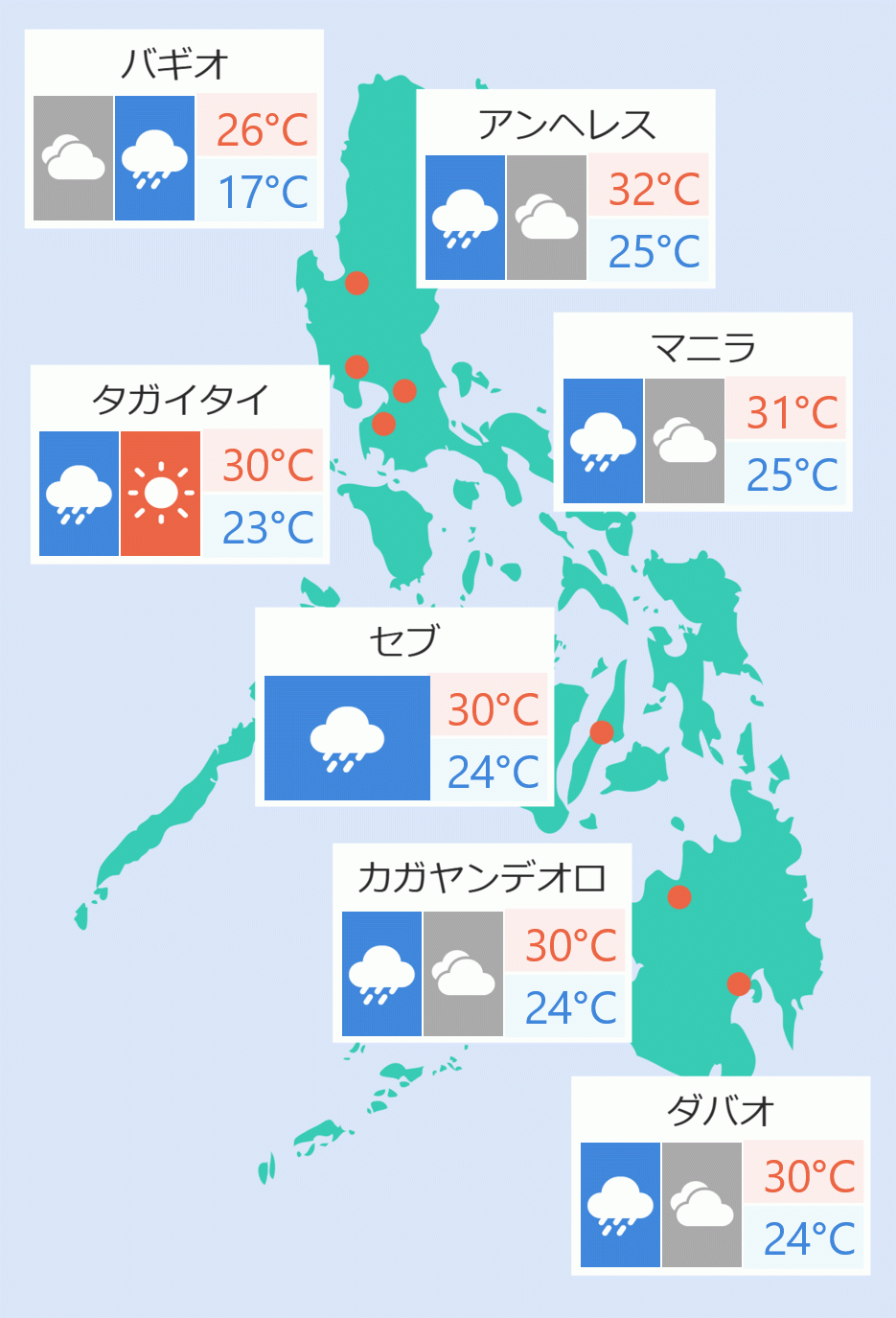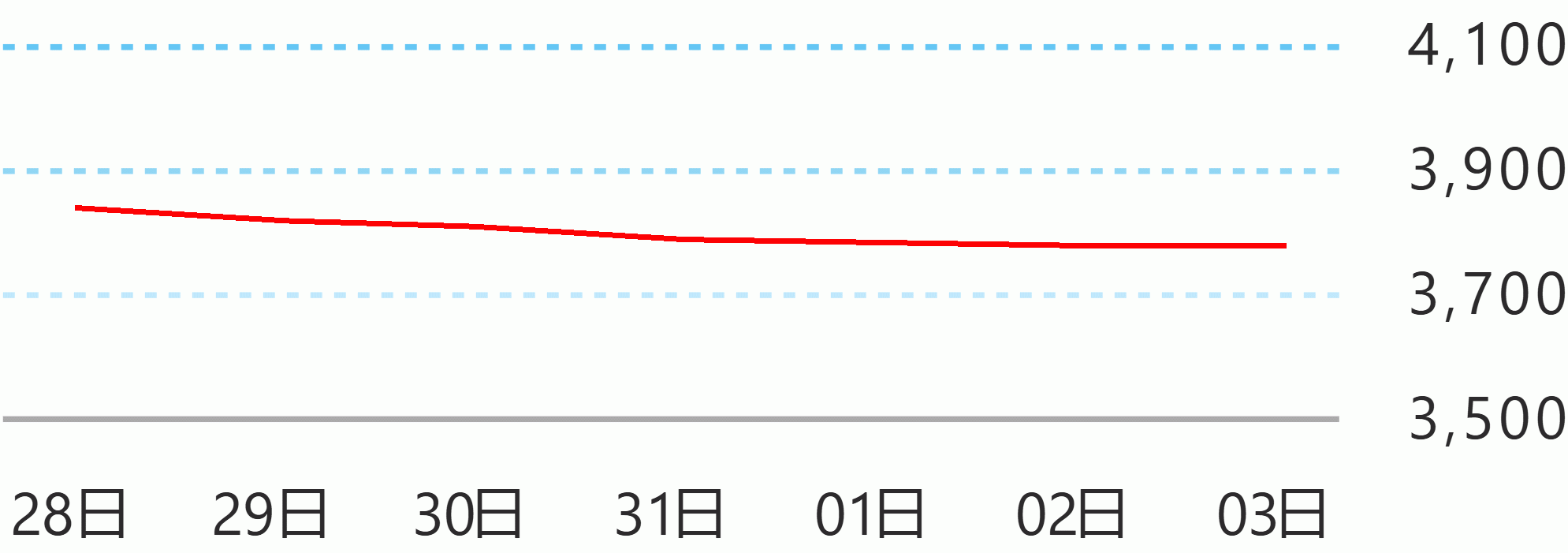第1回 ・ 沖縄移民2世の「古里」

二〇〇二年八月二十五日、フィリピン航空のチャーター便が沖縄・那覇からダバオ国際空港に着陸した。降り立ったのは「慰霊と交流の旅」に参加したダバオ生まれの日本人約百四十人。戦死した親兄弟を供養しようとする人がいれば、生き別れた幼なじみとの再会や、子や孫に生まれ育った山野を見せるために参加した人もいる。「旅」は戦後三十八回目。七十代中心の参加者に共通しているのは「来年はもう古里に来られないかも」という悲壮な思いだ。
ルソン島北部でベンゲット道路の建設が終わった一九〇五(明治三十八)年。前後してミンダナオ島南部ダバオ市では麻(マニラ麻)の栽培が始まり、日本人移民の受け皿となった。時代が戦争へと転がる中、軍需産業としての側面を持つ麻栽培は興隆を極め、同市在留邦人の人口は最大で一万九千人を超えた。
中でも沖縄出身者は「麻移民」の半数以上を占め「(本土から来た)日本人は不況時代に何の因果でかかる所に来たのかと気を腐らしたが、沖縄県人は蛇味線を弾き、好きな豚肉を味わい、平気で暮らして大きな勢力をなした」(古川義三著「ダバオ開拓記」)。
「旅」の参加者百四十人は、戦前入植した移民一世たちの子供にあたる。その一人、並里裕人さん(70)=那覇市小禄=の父は、市中心部で「並里旅館」を経営していた。旅館のあったマガリヤネス通りには、みそやしょう油を扱う「大力商会」、日本から輸入した中古エンジンや金物を扱っていた「竹川ハードウエア」、邦字紙「日比新聞」の社屋などが立ち並んでいたという。
同通りは当時と同じ名前で現存。地区の区割りも当時のままで、街角に立つと少年時代の思い出があふれ出てくる。「家の前はカナル(水路)で真っ黒なドンコ(ハゼ科の魚)が泳いでいた」「向かいのレストランに一杯十センタボのラーメンを食べに行った」「あそこの映画館ではマニ(落花生)を食べながら米国の喜劇映画を見た」・・。
戦前、通信社特派員として比に二年間滞在した故中屋健一氏が著書「フィリッピン」(四二年出版)の中で「商店街は横文字と日本語がチャンポンでちょうど軽井沢の本通りか横浜の弁天通りを歩いている気分」と記した風景。六十年以上を経た今も、並里さんの心の中では当時使ったフィリピノ語混じりで刻まれている。
並里さんが古里を去り、兄と二人で初めて両親の郷里・沖縄の土を踏んだのは開戦直前の一九四一(昭和一六)年十一月だった。「ダバオでは靴を履いていたのに、沖縄はみな裸足でイモを食っている。これでは勝てないと思った」。当時小学四年生だった並里さんの直感は的中し、ダバオの日本人社会は敗戦とともに崩壊。一人ダバオに残った父は敗戦間際に山へ逃げ込み、亡くなった。遺骨はない。
戦後、比の最高峰アポ山のすそ野から海岸に至る一帯を埋めていた麻山はヤシ林に変わり、旅館前を流れていた水路は埋め立てられ黒ハゼも消えた。父が命を落とした原生林の山は伐採ではげ山同然になった。「それでもね」と並里さんは言う。「生きている限りダバオに来る。私たち(移民二世)はここから生きていったのだから」 (つづく)
◇
年間企画「移民一世紀」の第二部では、戦前に比最大の日本人コミュニティのあった「ダバオ」を軸に、戦争で生き別れた人々や戦地に取り残された日系二世らの今を取り上げる。(酒井善彦)
(2003.4.14)





 English
English